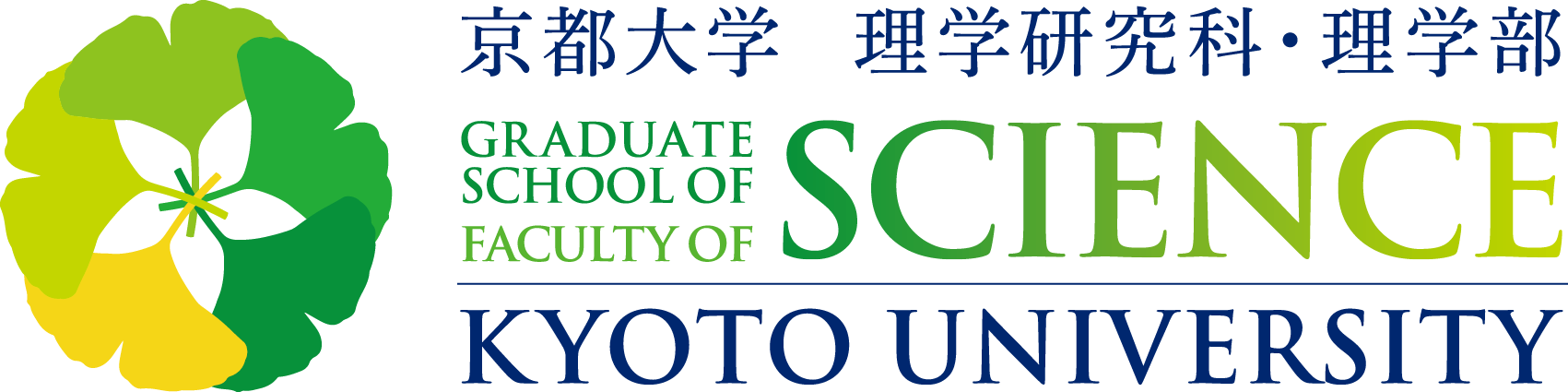募集要項
| 職種 | 准教授 |
|---|---|
| 募集人員 | 1名 |
| 勤務場所 | 京都大学大学院理学研究科附属サイエンス連携探索センター「以下、SACRA」 詳しくはhttps://sci.kyoto-u.ac.jp/ja/divisions/sacra をご覧ください。 (所在地:京都市左京区北白川追分町) (変更の範囲)大学が在宅勤務を許可又は命じた場合は自宅等 |
| 分野 | データ理学仮説創出、未踏量子計測、地球と生命の共進化のいずれかに関わる分野 |
| 勤務内容 | SACRAでは、研究展開セクションにおいて、データ理学仮説創出ユニット、未踏量子計測ユニット、地球と生命の共進化研究ユニットの3グループで融合領域の研究をスタートしました(注1)。本公募では、大学院生を含む研究グループを主宰し、また、当該分野に関わる新たな大学院講義(ゼミナールも可)を開講して、学際融合的研究を推進していただける方を募集します。指導教員として大学院生を指導していただく予定ですが、複数の専攻からの学生の指導に関わっていただく可能性があります。 |
| 資格等 | 博士の学位を有すること |
| 着任時期 | 決定後できる限り早い時期 |
| 任期または雇用期間 | 5年(再任は、学術的業績、教育及び運営への貢献、社会的貢献、再任後の研究計画等を勘案して判断) 再任後の任期は5年、1回に限り再任可 |
| 試用期間 | あり(6か月) |
| 勤務形態 | 専門業務型裁量労働制(週38時間45分相当、1日7時間45分相当) ・専門業務型裁量労働制を適用しない場合は、週5日8:30~17:15勤務(休憩12:00~13:00) 超過勤務を命じる場合あり 休日:土・日曜、祝日、年末年始、創立記念日 |
| 給与 ・手当等 | 本学支給基準に基づき支給 |
| 社会保険 | 文部科学省共済組合、厚生年金、雇用保険および労災保険に加入 |
| 応募方法 および 必要書類 |
下記(1)〜(6)の書類のPDFファイルを一つにまとめて圧縮(Zip形式)したうえで、JREC-INポータルサイト(https://jrecin.jst.go.jp/)から電子応募してください(Zipファイル名は「応募者氏名(アルファベット半角)_sacra 」)。その際、(6)以外の書類は単一の PDF ファイルにまとめ、(6)については論文ごとに別個のPDFファイルとしてくださ い。なお、各PDFのファイル名にも、応募者の氏名をアルファベット半角表記で含めてください。 応募書類: (1)履歴書(各項目は年月日まで記載のこと) (2)研究業績リスト(主要論文5編以内に丸印をつけること) (3)「これまでの研究内容の概要」及び「今後の研究計画の概要」(各2000字程度)。 (4)「学際融合研究・教育を行う抱負」について1000字程度 (5)本人について意見を求めうる方2名の氏名・連絡先 (6)主要論文(5編以内)の別刷 |
| 応募締め切り | 2025年6月27日(金)23時59分(日本標準時 JST)までに JREC-INポータルサイトへのアップロードを完了すること。 |
| 選考方法 | 書類選考および面接選考 |
| 問い合わせ先 | 〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学 大学院理学研究科 SACRAセンター長 坂上貴之 TEL:075-753-2660 E-Mail:sakajo.takashi.5z*kyoto-u.ac.jp(*を@に変えて下さい) |
| その他 | ・SACRAが理学研究科の分野を横断する組織であることと関係して、SACRAに勤務するすべての教員は 、令和7年度は生物科学系所属となります。その後は、理学研究科の規則に従って、所属する学系が変更となります。 ・提出していただいた書類は、採用審査にのみ使用します。正当な理由なく第三者への開示、譲渡および貸与することは一切あり ません。 ・本学における男女共同参画推進施策の一環として、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男 女雇用機会均等法)」第8条の規定に基づき、選考において評価が同等である場合は、女性を優先して採用します。 ・京都大学では教育・研究および就業と家庭生活との両立を支援いたします。 https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/ ・出産、育児又は介護により研究を中断した期間がある場合は、応募者の申し出により研究業績の審査において考慮します。応募 書類に明記して下さい。 ・京都大学では、すべてのキャンパスにおいて、屋内での喫煙を禁止し、屋外では喫煙場所に指定された場所を除き喫煙を禁止す るなど、受動喫煙の防止を図っています。 ・京都大学大学院理学研究科は、研究活動におけるコンプライアンスに対する教職員や学生の意識の向上に努めています。 注1)SACRA研究展開セクションの詳細 SACRAは、理学研究科の5つの専攻の複数分野にまたがる学際的な研究・教育活動を推進し、また、これらの専攻の研究領域を横断 する各種事業を企画し実施する組織として、2019年に設立されました。学際的な研究・教育活動の推進は、学際融合部門が担っており、代表的な教育活動として「数理を基盤として新分野の自発的創出を促す理学教育プログラム」(MACS教育プログラム) を実施しています。 https://sci.kyoto-u.ac.jp/ja/academics/programs/macs/sg 2024年度からは、このMACS教育プログラムに加えて研究展開セクションを新設し、その中に以下の3つの研究ユニットを設置しま した。2025年度には、各ユニットに教授または准教授のユニット専任教員が新たに着任し、様々な専攻の教員と協力して研究・教 育を展開しようとしています。 https://sci-section-kyoto-u.studio.site/ 1. データ理学仮説創出ユニット 基礎科学の多様性とその連携を活かして「理論から応用、実践まで」を包括的にしたデータ科学時代の新しい学理の探求と諸分 野への展開のため研究を行う。従来の、実験や観測によって得られたデータから仮説を創出し、そこから理論を作り演繹して予言 し実験や観測で確認するという人的サイクルとは異なり、大量のデータから支配方程式や因果推論を構築する研究を推進する、新 しい時代の「データ理学仮説創出拠点」である。データから仮説を創出する過程を体系化する学理の探求は、現在の理学の一部を 大幅に加速する可能性を秘めており、自然法則の発見自体を創発現象として記述するメタ理学の構築へと通じる。 <研究テーマの例>機械学習による仮説創出のメタ理学の研究、地球生物圏の未来予測に関する基本的限界を定式化するデータ科 学の構築、仮説創出の科学哲学・認知を応用した機械学習手法の開発、莫大なデータと統計的手法の機械学習的融合研究など 2. 未踏量子計測ユニット 未開拓な周波数領域の光子の光源や検出器の開発を進めるとともに、物理計測、生体イメージング、分光計測などの計測に関わる 新規なアルゴリズムや機械学習を利用した大規模データ解析などの研究開発も進める。また、先端的な電子ビーム等を用いた高解 像度電子顕微鏡の開発も行う。光や電子などの量子としての性質を使った「量子波計測」の発展によって、人類がこれまで見るこ とが出来なかった世界が見えるようになってきた。そして今、計測データを処理するコンピュータアルゴリズムの進化や量子コン ピュータの発展によって、計測にもさらなる進化が待望されている。そのための、「新たな目」(=量子波先端計測)の開発が急 務であり、本ユニットでは世界に先駆けて、その開発と応用を実践していく。 <研究テーマの例>宇宙と物質の根源をみる量子プローブ開発、量子性際立つ超低温環境での物性分析、量子センサーによる生体 計測など 3. 地球と生命の共進化研究ユニット 人類の時間スケールを超越した久遠の地球未来像を考究するためには、生物進化や地球史、データ科学に関わる諸分野の専門家が 一堂に会する教育研究組織が必要である。それらの専門家が参画し、様々な時空間スケールでの生命現象と地学現象の関連を探索 し、生物進化と環境変動の相互作用の解明を目指す。 <研究テーマの例>生物進化過程と地球環境変動の長期的相互作用の研究、ジオ・バイオ・インフォマティクスによる生物進化史 の復元、分子・機能・形態・生態の階層統合的解析など |