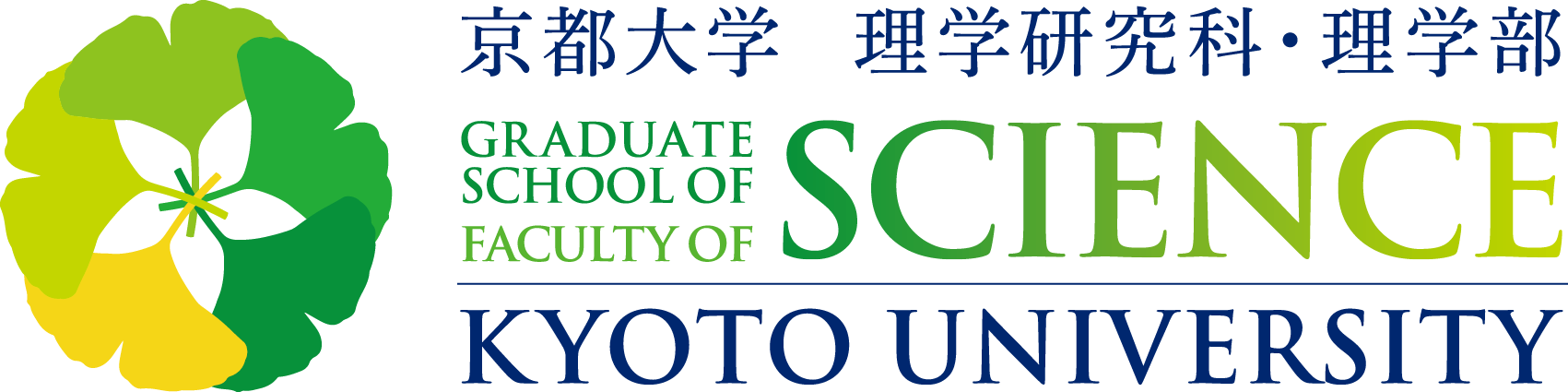長田:はい。宇宙物理学教室の長田でございます。私の専門は一応、赤外線天文学という名前になっておりますが、最近はどちらかというと望遠鏡を作るというプロジェクトを主にやろうとしております。多分今からちょうど100年ぐらい前までは、天文学っていうのは、別に大きな望遠鏡を作るという方向には走ってなかったと思うんですが、1920年、30年頃から、どんどんどんどん大きな望遠鏡を作るというふうになってきました。で、赤外線天文学に関して言うと、赤外線で天体を見るというのは、一番最初は、1800年ちょうどの時に、ハーシェルが太陽の光をプリズムで分けて、赤よりも外のところで一番エネルギーが来てるというふうにやったのです。だけど、1900年になっても、1950年になっても、赤外線のセンサーというのは全然発達しなかったので、天文学はほとんどできなかった状態でした。それが1960年頃から半導体の技術が発達して、赤外線のセンサーを望遠鏡の後ろにつけると、赤外線で星が見えるという時代になってきました。最初は、いわゆる天文学の教室みたいなところじゃなくて物理学者がそういうことをいちびってやり始めたわけです。普通の光の望遠鏡に少し工夫して、赤外線が感度良く受かるという第一世代の望遠鏡を世界のいくつかの場所で作り始めた頃に、京大が物理学第二教室で、木曽の上松というところに1メートルの望遠鏡を作ってやり始めたというのは、なかなか先進的なことだったと思います。しかしその後、日本は大きな望遠鏡がなかったので、かなり世界に水を空けられたみたいなことになっていたんですが、1999年にすばる望遠鏡をハワイのマウナ・ケアに作るということで、また復活して今はかなりすごいことになってるという状況だと思います。ただ、そういうわりあい初期の頃からの人間にとってみると、やっぱり観測装置を作ったり、あるいは望遠鏡を作ったりしてやっているというのが、性に合っていることもあります。それで、そのすばる望遠鏡ですべてをやってしまってるという日本の状態はよくないと思うんです。アメリカにしても、ヨーロッパにしても、たくさんの小さな望遠鏡、1メートルくらいの口径の望遠鏡から、それから2メートルクラスがあり、それから4メートルクラスがあって、そして8メートルとか10メートルがあって層の厚い研究をやってます。向こうはこう、船団でやってくるわけですね。それが日本は単に戦艦大和が1隻あるだけという状況なので。
三輪:なるほど。
長田:だから、ちゃんと京大でも4メートルクラスを作ろうということで、3。8メートル望遠鏡計画というのを進めておるわけです。その中でサイエンスとして何をやっているかというのをひとことだけ言いますと、私自身の興味の一つは、銀河系の中心部です。我々は、銀河系の中心で一体何が起こってるか、星がどういうふうに生まれてるかといったことをやろうとしてます。この間も、3。8メートル望遠鏡っていうのは、どこまで見えるんですかと聞かれました。宇宙が始まってからだいたい137億年と言われてますので、光の速さで137億年行ったところが、一番向こうなわけです。だから、137億光年の場所まで見えるというのが理想的な望遠鏡なわけですが、すばる望遠鏡など大きな望遠鏡だと、ほとんどそこまで見えてるんですよね。130億光年ぐらいの距離まで見えています。3。8メートル望遠鏡でもそれぐらいまで見えるはずなんですよね。明るい天体があれば、ちゃんと見えると。だけど、我々は銀河系の中に住んでいるので我々のところから中心を見通そうとすると、実は光はやってこないんですよね。なんでかというと、宇宙空間はdustyで、「宇宙塵」と呼ばれる固体微粒子がいっぱいあるので、全然見通せないわけです。そこで赤外線の出番なんです。赤外線で見通すと、銀河系の中心まで見えるんです。太陽の400万倍の質量のブラックホールがあるということが、だいたいわかってきました。しかもそのブラックホールというのが、周りからガスを吸い込むと、時々光るんです。宇宙には、そういうブラックホールに常時ガスが落ちていって、ものすごい光を出してる天体もいっぱいあるんですが、我々の銀河系の中心はそうではなくて、ほとんど光っていません。ところが時々は光るんだということが最近わかって、すばる望遠鏡でモニターをして詳しく調べています。それから実は、今年の夏ごろにガスがボーンと落ちていくということが予測されていて、それを今年はちゃんと見たいもんだなと思っています。
西村:壮大な感じがしますよね、宇宙っていったら。
西村:教授会で宇宙物理学教室の調査報告で、「うちゅうじん。。。」と読み上げられると、分野外の私は直ぐに別の「うちゅうじん」を想像してしまいます。すみません(笑)。