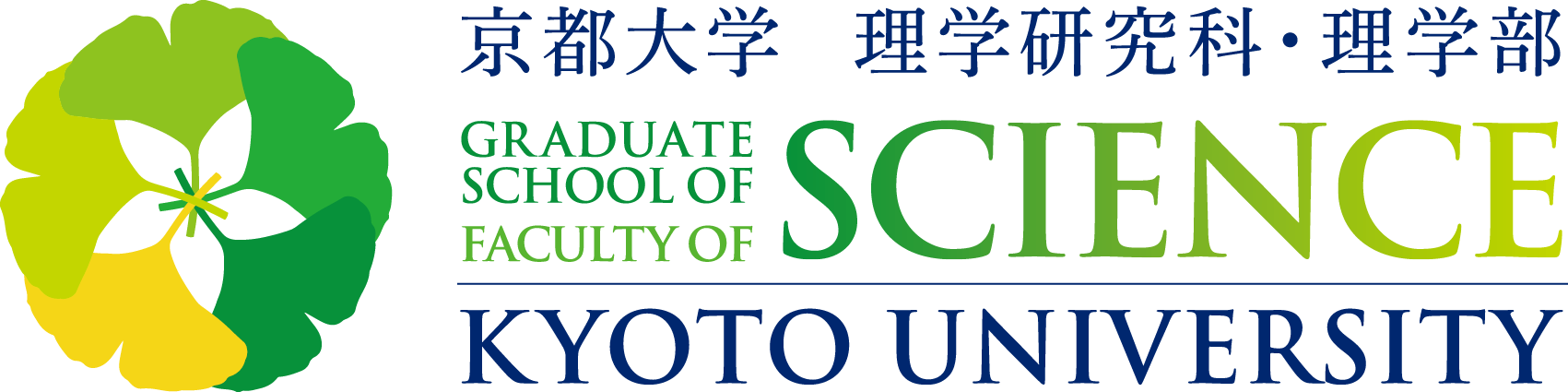企画名
| 生命のダイナミクス:本物を観て(観察)考える(数理) |
参加教員
| 教員名 | 所属 | 職名 |
|---|---|---|
| 高橋淑子(代表教員) | 生物科学専攻 | 教授 |
| 國府寛司 | 数学・数理解析専攻 | 教授 |
| 荒木武昭 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 准教授 |
| 伊丹將人 | SACRA | 特定助教 |
| 稲葉真史 | 生物科学専攻 | 助教 |
企画の概要
生き物の成り立ち(発生など)の過程では、細胞や組織は刻々とその形や性質を変化させる(生命のダイナミクス)。そして隣り合う細胞とネットワークを創り上げ、高次の生命機能を可能とする。本SGでは細胞生命ダイナミクスをテーマにして、その理解を深めるために分野を超えた議論を試みる。まず実際にどのような細胞生命ダイナミクスがあるのかを知る(観る)。次にそのダイナミクスの理解を深めるための数理的アプローチを考える。メカノバイオロジー、神経ネットワーク、オシレーション(心拍、概日リズム、腸蠕動運動などの振動現象)などをキーワードにして、実験科学(Wet)と数理科学(dry)の融合による相乗効果を体感する。論文をじっくり読み込みながら、教員と学生が一緒になって理解を深める。また院生が自分の研究プロジェクトを学部生に紹介するなどして、学生間の「縦の」つながりを醸成したい。関連する研究者を外部より招へいし講演会を開催する。単位や成績はなし。議論しながら学問する楽しさを求めたい
説明会資料
4/19(金)のスタディグループ説明会資料はこちら
実施期間・頻度
原則として金曜日の5限。2−3週間に1度程度の頻度で、論文輪読会やディスカッションMeetingを行う。また半期に1度は実習室で「本物」の胚と向き合う。
TA雇用の有無
原則なし
その他、特記事項など
実際の胚(主にニワトリ胚)の観察や操作のために、顕微鏡などの備品が必要である。できるだけ現存機器を活用するが、本SGに特化した実習のために関連器具(顕微鏡アクセサリーなどの小器具)などが必要になる可能性がある。ニワトリ受精卵、培養液、試薬等の購入が必要。
問い合わせ先
yotayota[at]develop.zool.kyoto-u.ac.jp([at]を@に変えてください)
あるいは
takahashi.yoshiko.5c[at]kyoto-u.ac.jp([at]を@に変えてください)
スタディグループへの登録は締め切りました。
関心のある方は macs *sci.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)までご連絡ください。
活動報告
活動目的・内容
<目的>
多細胞生物における形態形成のダイナミクスをテーマにして、その理解を深めるために分野を超えた議論を試みる。
<内容>
① 大脳皮質に見られる「しわ」が作られる仕組みを皮質の物理特性から解析した論文[1]と眼杯の凹みができる仕組みを実験と数理モデルから解析した論文[2]を学部生および院生を中心に輪読し実験データや使用されている数理手法について深く議論した。
[1] Tallinen, T., et al. (2016). On the growth and form of cortical convolutions.
[2] Okuda, S. et al. (2018). Strain-triggered mechanical feedback in self-organizing optic-cup morphogenesis.
② ①で読んだ論文と関連する生命現象の本物を観るために、生きたニワトリ胚を用いた実習を行った。ニワトリ胚の観察手法を学び、発生過程の脳を取り出しヒトの脳との違いを理解した。また、[1]論文で取り上げられていたゲルを用いた物理実験を行い、ゲル表面に脳のしわに類似したしわパターンを作ることを観察した。
③ 国内および海外の研究者を招聘して最新の生物学研究の動向を紹介して頂いた。また生物データを解析する上で有用な生成AI技術の応用についても解説して頂いた。
12/4 Yasuko Akiyama-Oda博士、Roberto Mayor教授、Kazuhiro Aoki教授、Alessandro de Simone博士、Takahumi Ikeda博士、Vanessa Barone博士、Angela Nieto教授。
2/4 中川真一 教授
④ 参加メンバーの伊丹氏に、形態変化のシミュレーションとそれを実行するためのプログラミング技術についてレクチャーして頂いた。
活動成果・自己評価
① [1]の論文では、ヒト大脳皮質のしわ形成が接線方向に成長した皮質の圧縮で説明できることを明らかにした。輪読を通じて、脳の解剖学的特徴、しわ形成機構が生物学的に未解決であること、しわ形成のような組織変形を物理的に記述する方法論について学んだ。[2]の論文では、眼杯(凹の形をとる)の自律的形成が組織から細胞へのロバストなフィードバック機構に制御されることを学んだ。
② 実際に自分自身の手を動かし、生きたニワトリ胚を観察することができた。実際の組織を観察する際の難しさや、可視化を可能とするちょっとしたテクニックについて実感してもらったと思う。またゲルを使ったしわ形成の物理実験にも取り組んだが、膨潤によりシリコン半球が土台から剥がれる、有機溶媒の揮発が想定以上に早いなど、輪読だけでは分からない難しさがあることを知った。
③ 海外および国内の著名な研究者による最新の研究成果に触れることができ、学生だけでなく教員にとっても良い刺激となった。特に海外の研究者は自身のアイデアを聴衆に分かりやすく伝えようとする熱意がすごく、彼らのプレゼンスタイルについては学ぶことが多いと感じた。
④ 参加メンバーの伊丹氏から物理シミュレーションの手法について未経験者にも分かりやすく解説して頂いた。プログラミングが決して難しくないことを簡単な例を取り上げつつ解説して頂き、学部生のこれからの学習、研究に大いに参考になったと思われる。
SG活動に関する写真・図

実習の様子

実習で観察したニワトリ脳

ゲルを使ったしわ形成の物理実験


参加メンバー
| 松井健安 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 修士1回(M1) |
| 栁澤優介 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 博士2回(D2) |
| 山﨑遥平 | 理学部 | 学部2回(B2) |
| 宇都宮翔大 | 生物科学専攻 | 修士2回(M2)以上 |
| 嶋田佐津 | 理学部 | 学部2回(B2) |
| 近藤淳史 | 数学・数理解析専攻 | 博士1回(D1) |