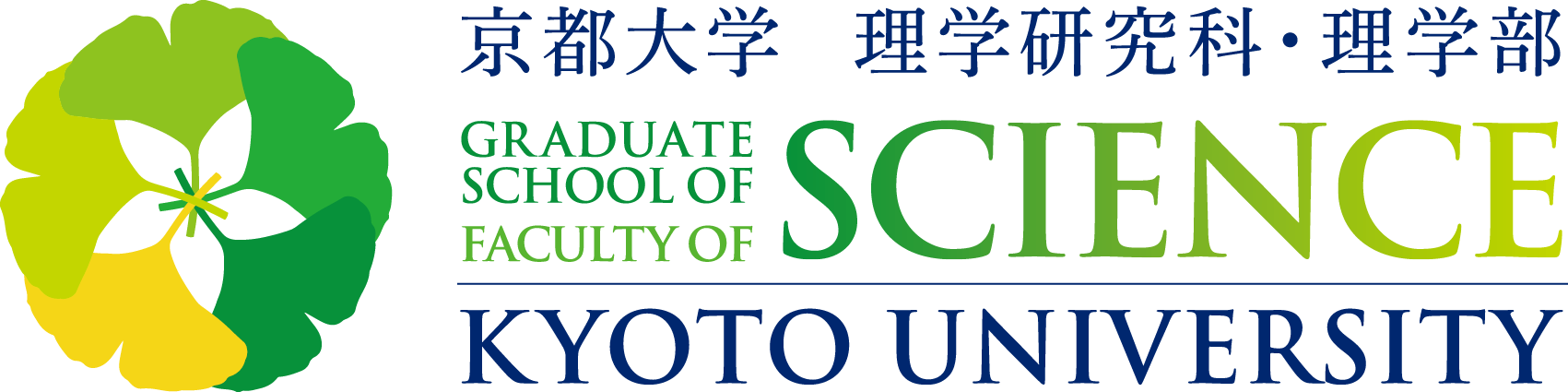理学研究科と京大オリジナル株式会社は、高度科学人材の育成とイノベーションの創出を目指して「京都大学理学共創イノベーションコンソーシアム」を産業界と共に推進しています。コンソーシアムでは研究交流会を開催し、優れた研究発表を行なった大学院生を顕彰し、「理学研究科銀楓賞」を授与しています。
令和7年2月に開催された第4回 研究交流会では学生らによるピッチコンテストとポスター発表がそれぞれ30件以上も行われ、その中から8名の学生が受賞者として選ばれました。(当日の様子はこちら)
本賞の表彰式は令和7年3月21日に理学研究科1号館にて執り行われました。受賞者に対して、田中耕一郎研究科長より表彰状が手渡されました。続いて、受賞者からスピーチがありました。研究交流会での気付き、企業の方や他専攻学生に研究成果を説明する難しさなど、それぞれが感じたことを伝えていました(司会は森脇一匡 理学研究科・教授)。
受賞された方々と、その対象となった研究発表演題は以下のとおりです。
研究発表演題
- 鈴木 隆人(物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野)
「円盤積み上げにおける力の記憶制御の定式化」 - 石田 祐(生物科学専攻 動物学系)
「神経中胚葉前駆細胞の進化的起源」 - 鈴木 飛翔(生物科学専攻 霊長類学・野生動物系)
「培養細胞系を駆使したホッキョクグマ寒冷適応型代謝メカニズム解明に向けて」 - 岡本 優芽(生物科学専攻 霊長類学・野生動物系)
「ネコはなぜヒトとひとつ屋根の下で暮らしているのか~社会性の遺伝的背景~」 - 森川 晏吾(生物科学専攻 動物学系)
「ヘビ類におけるヒキガエル毒の代謝機構の解明」 - 奥田 尚(数学・数理解析専攻 数理解析系)
「マントル対流の熱対流構造の数理解析」 - 野口 貴志(数学・数理解析専攻 数理解析系)
「最小2辺連結全域部分グラフ問題に対する近似アルゴリズム」 - 古城 侑季(地球惑星科学専攻 地球物理学分野)
「イオノゾンデ受信機網観測によるスポラディックE層の水平移動・水平構造の研究」
画像

左から順に、奥田尚さん、森川晏吾さん、石田祐さん、鈴木隆人さん、田中耕一郎研究科長、植松亮祐さん、古城侑季さん、野口貴志さん。
写真下|
左から順に鈴木飛翔さん、岡本優芽さん。お二人はご都合がつかず欠席されましたので別途お渡ししました。
植松亮祐さんは前回の受賞者。前回の授賞式に欠席されたため、今回お渡ししました。