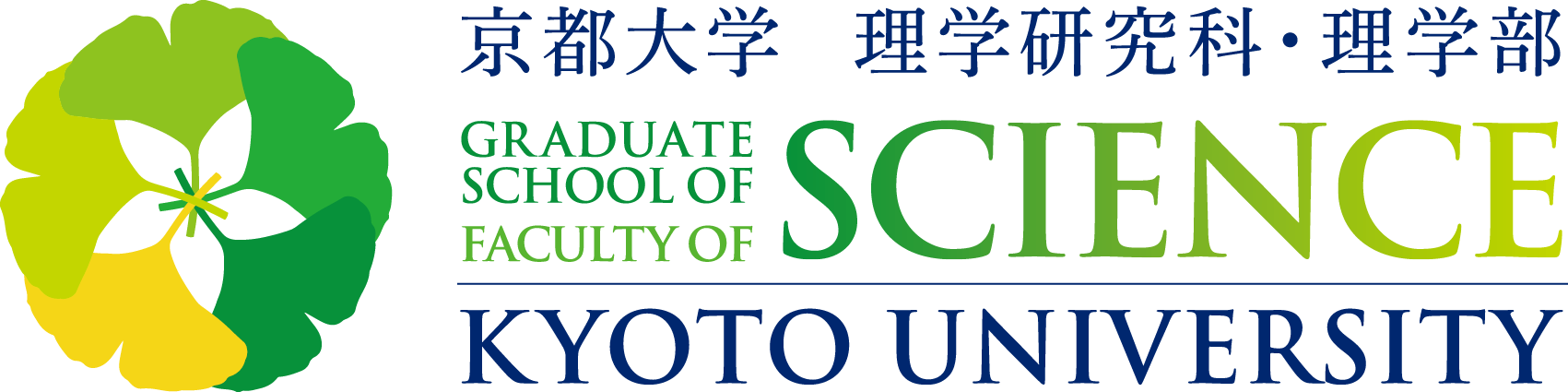藤田 遼
今日、コンピュータは数学の研究に大きく影響している。「平面上のあらゆる地図は、四色を使って塗り分けられるだろう」といういわゆる四色問題が、コンピュータを用いずには解き得なかったという有名な歴史的事実は、このことを象徴的に示す。
ところで近年、人口知能(AI)の発展が話題を呼んでいる。2016年にはAIが囲碁のトップ棋士に勝利するなど能力の高さを示した。2045年にはAIが「人間の能力を超える」と予想する人々までいる。ならば、AIという新たな技術は、数学の研究においても、コンピュータとは比べ物にならないほど大きな影響を及ぼすだろう。
数学は、基本となる最小限の約束事に則って論理を積み重ねてできている。その意味では、囲碁と同じように、ルールを持つゲームのようなものにも見える。だとすれば、「人間の能力を超えた」AIは、将来数学者にとって代わり、数学を研究するようになると期待したくなるだろうか。
確かにAIは非常に高い情報処理能力を持つ。このまま進歩すれば、計算能力やパターン認識能力において、人間はAIに到底かなわなくなる。ただ、AIは人間から明確な目標が与えられて初めてその高い能力を発揮できる。囲碁の場合には勝利という明確な目標があり、方法も最初から限定されている。四色問題の場合にコンピュータが有効だったのも、解くべき問題が明確だったからだ。
数学者は問題を解くだけでなく、問題を作らなくてはならない。数理的事実を目の前にして、それをどう理解したいかという主観に根ざして、必要な数学的概念を拵え、できるだけ明確で本質を捉えるような良い問題を探す。例えば5次方程式に解の公式がないことを理解するために、ガロアは解のもつ対称性を捉えるための群という概念を導入し、ことの本質を明確にした。単に「解の公式がないことを証明せよ」という問題を解くのでなく、その背後にある対称性から事実を理解しなおそうと思わなければ、このようなアプローチはとれないだろう。
問題解決のための直接的方法を既存の知識から探したり、膨大なデータからパターンを抽出する際には、AIは強力な道具となるかもしれない。だが、AIは我々に多くの数学的事実を提供こそすれ、それをどう捉えるべきか、というより重要な問題は、AIではなく数学者がその主観において取り組まなくては意味がない。