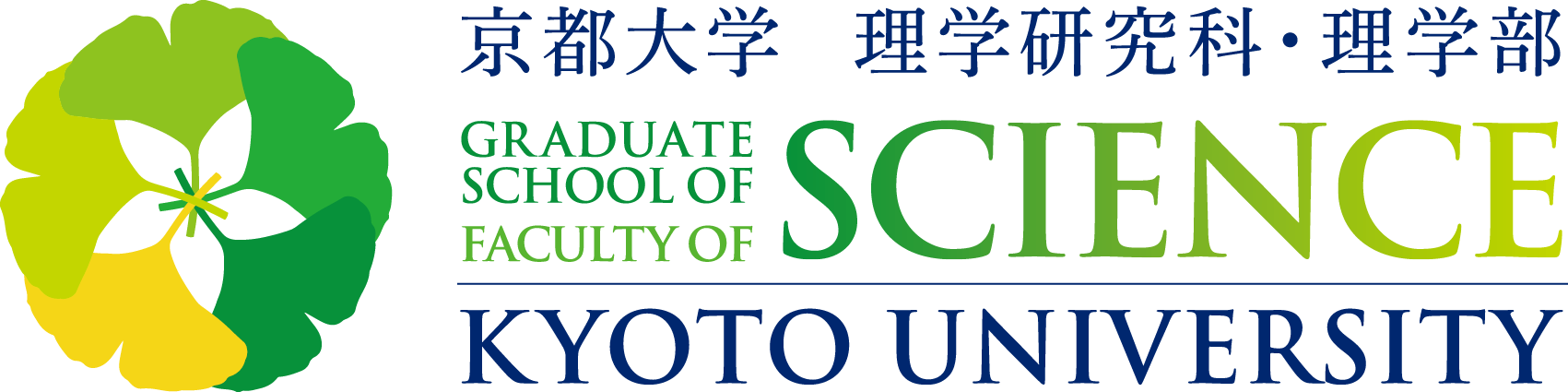化学専攻・理論化学研究室・准教授・倉重佑輝

以前、数ヶ月の短い期間ながら神戸の自宅から吉田キャンパスへの長距離通勤をしておりました。距離的には神戸から京都駅までを10とすれば、京都駅からキャンパスまでは1と1/10でしかありませんが、かかる時間は体感として京都駅までで半分、そしてキャンパスもう半分というぐらい京都駅からのアクセスの悪さに難渋しておりました。当初はそんな風に立地だけには多少不満を持っておりましたが、引越しも落ち着き研究生活に安定がもたらされると、それはつまり見通しの悪い試行錯誤を嫌気のささないように工夫して過ごす毎日な訳ですが、嫌なことは忘れてなんとも落ち着いた気持ちになれる鴨川への散歩のアクセスの良さが最大の立地の良さであると思うようになりました。そんなある日、散歩が過ぎてかなり南に下ったところ、頭に三角の網代笠をちょこんと乗せて両手には10mを超える長ーい竿を携えた釣り人が流れの中に立っている時代物の撮影のような風景に遭遇しました(実際、鴨川では何かの撮影現場に出くわすことも多いです)。残念ながら釣れた瞬間には立ち会えなかったので、その時は何を狙っているのか分かりませんでしたが、戻って調べてみるとどうやら鮎の友釣りというものだったようで、遠く大阪湾から遡上してきた僅か十数cmの魚が囮と呼ばれるもう一匹の哀れな同胞を十mの竿で操る人間に狙われていたと考えればなんとも可笑しくてしょうがありません。それ以降、鮎という魚に興味を持ちまして、ここで数々の推しポイントをご披露したい所ですが誌面の都合もありますのでそれは自重するとして、本業の研究とは結びつかなくても多くの出会いのある鴨川散歩、あまり研究室から出ない生活をしていると京都駅はおろか鴨川ですら遠く感じるようになっている昨今ですが、春夏秋冬全てに季語を持ち一年で生涯を終える潔い年魚、鮎と共に推させて下さい。