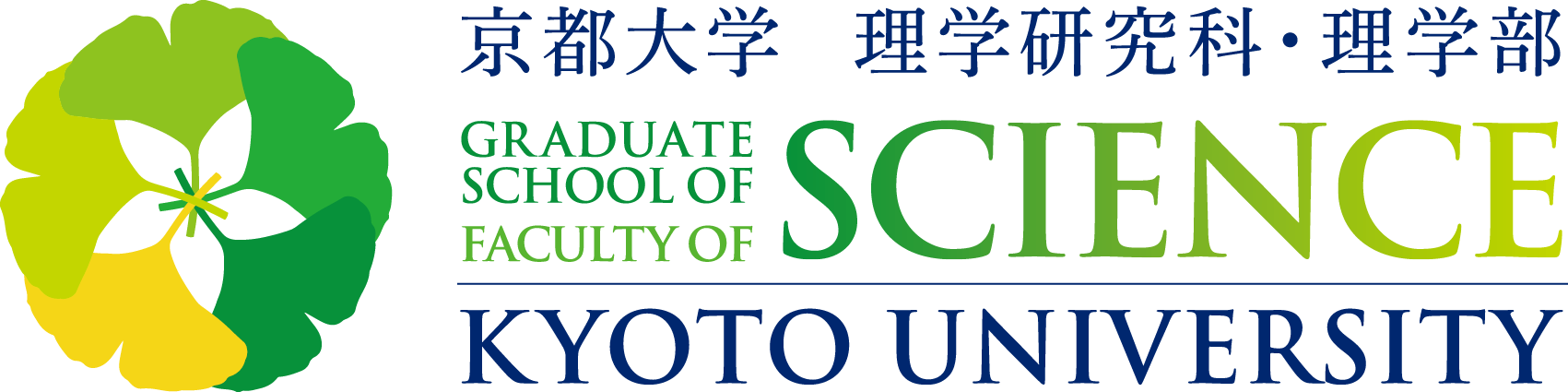名誉教授・動物学教室出身 疋田 努

蜥蜴(せきえき/トカゲやカナヘビを指す)や蝘蜓(えんてん/ヤモリ類を指す)に朱を沢山食べさせ、赤くなったものをすりつぶしたものを女人の体に付けると、洗っても終年落ちることがないが、房事があれば消えるという。この赤い印を守宮砂(しゅきゅうさ)という。この動物を守宮と呼ぶのは、後宮を守るという意味で、東方朔が漢の武帝に勧めて効果があったという。この話はずいぶんと有名で、南方熊楠の随筆にも晋の張華の博物誌が引用されている。
平安時代にはこの話はよく知られていたらしく、「いもりのしるし」として和歌にも見える。この「いもり」がヤモリの古い名なのか、イモリととりちがえたのかが問題になるが、百人一首の「むらさめのつゆもまだひぬ…」で有名な歌人である寂蓮法師の和歌に、「ゐもりすむ山下水の秋の色はむすぶ手につくしるしなりけり」というのがあり、これで明らかにイモリを指していることがわかる。
京都市内では、大学の周辺でも多くのヤモリ(標準和名はニホンヤモリ)が見られる。この種は在来種とされてきたが、外来種の可能性が指摘されており、それがいつ日本に侵入し分布を拡げたかを文献で調べていて、この守宮砂の話を見つけたのである。
古文献を調べると、「やもり」という名が初めて現れる文献は、ポルトガル人の宣教師らがキリスト教の布教のために作成した日葡辞書(1603)である。守宮については、「常在屋壁故名守宮也」と、和名類聚抄(938)にも唐代の蘇敬の新修本草(659)が引用されている。壁にとまっているニホンヤモリがいれば、守宮に間違いようがない。平安時代にはニホンヤモリがまだ分布していなかったので、朱色の腹をしたイモリ(標準和名はアカハライモリ)を守宮と取り違えたのであろう。
これらの文献から、ニホンヤモリが中国東南部から日本に入ってきたのは、南蛮貿易が盛んだった室町時代から安土桃山時代と推定される。江戸時代の本草書ではヤモリとイモリを明確に区別している。人見必大の本朝食鑑(1697)によると、京師(京都)、五畿(山城、大和、河内、和泉、摂津)、西国(九州)で見られるが、江東地方(関東)ではまだ見ないと書かれており、まだ東の分布を拡げていなかったらしい。
DNAデータによる系統推定や化石や遺跡から動物の過去の歴史を調べることができるが、比較的近い過去については、古文献、方言学、本草学や和歌までが役に立つのはなかなか面白い。