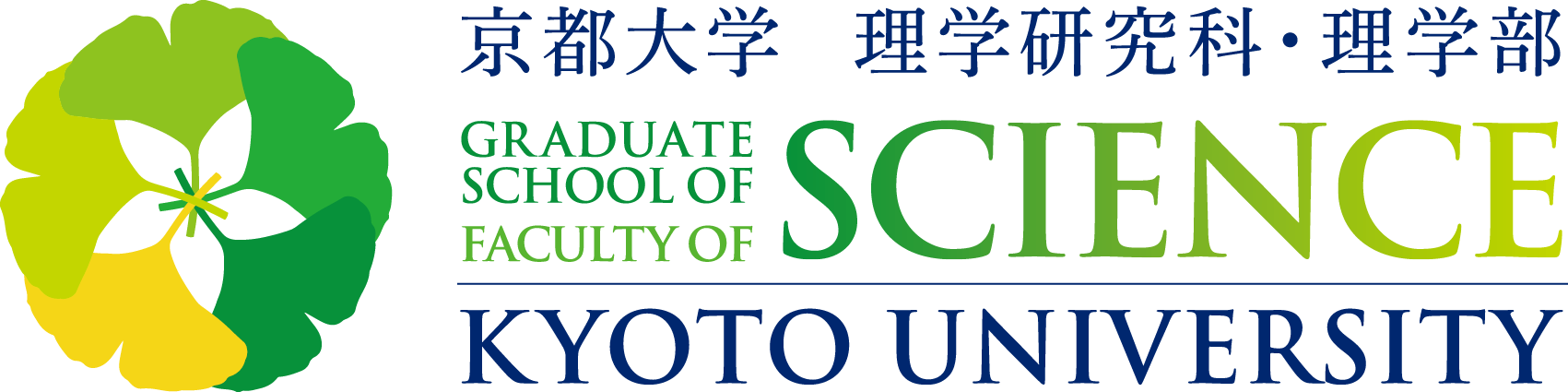平賀 椋太 生物の仕組みについての勉強が、世の中の役に立つという例として、エイズの薬、逆転写酵素阻害剤ジドブジンを紹介したいと思います。 …
サイコム
 抗エイズ薬のしくみ
抗エイズ薬のしくみ  ダーウィン医学
ダーウィン医学 小長谷 達郎 大正時代に大流行し世界で1億人もの死者を出したスペイン風邪——。その原因となった強毒性インフルエンザは、流行当初、…
 世界をがらりと変えたワールドワイドウェブ
世界をがらりと変えたワールドワイドウェブ 廣田 誠子 宿題で調べ物をしたい時、友達と遊びに行く場所を探したい時、昔は図書館や本屋で情報を探すのが主流でしたが、…
 GFP の発見と意外で偉大な応用
GFP の発見と意外で偉大な応用 西村 理沙 2008年、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見でノーベル化学賞を受賞した下村脩教授(1928年生まれ)の研究を紹介します。 …
 ピロールイミダゾールポリアミドとPeter B Dervan 教授
ピロールイミダゾールポリアミドとPeter B Dervan 教授 橋谷 文貴 カリフォルニア工科大学のPeter B Dervan 教授はDNA に結合できる化学物質、ピロールイミダゾールポリアミド(PIP)の生みの親です。PIP…
 V. Pestun
V. Pestun 浜 直史 素粒子論の研究目的は人類の知的好奇心の満足だ。特に、超弦理論と呼ばれて研究されている理論は、完成すれば世界中のあらゆる現象を説明できると考えられてはいるものの、…
 S. G. Srivatsan
S. G. Srivatsan 平賀 椋太 リシンという毒物があります。トウゴマという植物の種に含まれていて、バイオテロを意図してホワイトハウスに送り付けられたこともあるものです。 …
 素粒子は何世代? Rolf Dieter Heuer
素粒子は何世代? Rolf Dieter Heuer 廣田 誠子 欧州原子核研究機構(CERN)の機構長、Heuer 氏は、かつてOPAL という実験グループを率い、「素粒子の世代数」を明らかにしました。 1930…
 マーティンの鉄仮説
マーティンの鉄仮説 山方 優子 米国の海洋学者ジョン・H・マーティン博士は、鉄を通じて生物動態、地球温暖化問題を考えた第一人者です。博士の研究は私の研究と深く関係しています。 …
 森和俊教授
森和俊教授 竹村 毬乃 昨年アメリカ医学会で最も権威のあるラスカー賞を受賞した研究者がいる。理学部生物物理学教室の森和俊教授だ。研究テーマは「小胞体ストレス応答」である。 …
 有機化学者 バリー・シャープレス
有機化学者 バリー・シャープレス 齊藤 颯 アミノ酸や糖などの物質には、右手と左手のように立体では鏡写しの関係になっている分子の組が存在します。光学異性体と呼ばれるこのペアは、…
 理学研究科生物化学研究室の紹介
理学研究科生物化学研究室の紹介 橋谷 文貴 私たちの体は細胞と呼ばれる小さな袋状構造の集合体です。皮膚は皮膚細胞が、神経は神経細胞が集まってできています。様々な種類の細胞によって私たちの体はできているのですが、…