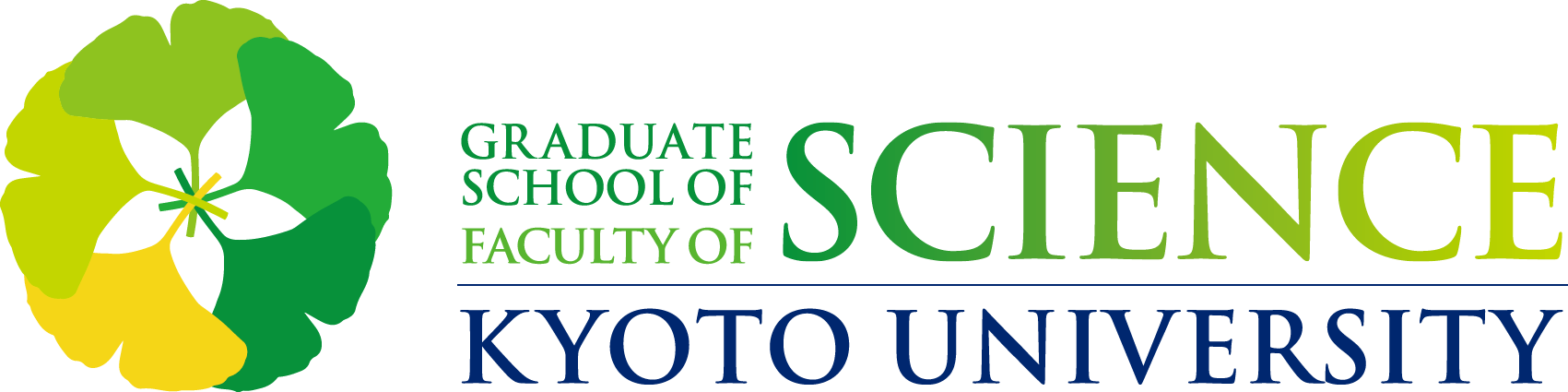神野 裕貴
現代に生きる私たちにとって理科は消費選択や政策決定において欠かせないものとなっている。しかし、学校教育を受けたからと言ってすべての人の社会的、文化的生活の中に理科がしっかり息づいているかというと疑問が残る。学生時代にどのようなことを身につければ、或いは教師の立場に立てばどのようなことを生徒に身につけてもらえばよいのだろうか。
学校教育においては各科目・単元ごとの細かな知識の理解や活用よりももっと大きな括り「科学的な認識」を伝えることに重点を置くべきだと考える。1963年に板倉聖宜氏が提唱した仮設実験授業という授業理論ではまさにこの「科学的な認識」が強調され、それを問題提起・予想・討論・実証実験の流れで身につけさせていく。漢字における常用漢字のように、最小限のもので幅広い科学的内容に触れる素地を養える「常用科学」として相応しいはずだ。
遠く異境を訪えばイギリスにこのような例がある。1985年、イギリス王立協会の小委員会は”The Public understanding of science”というタイトルの報告書を公表した。このタイトルの中の”understanding”という語は単に知識理解ではなく科学的活動や探求に関する理解という解釈がなされている。さらに特筆すべきはこの”understanding”の程度が個人の目的に依存しているということだ。つまり大衆”The Public”の社会的な役割などによって科学を知ることの理由が異なる、ということを考慮に入れているのだ。確かに知識をベースに考えるとそれを使う人と使わない人で差が生じてしまう。法則や原理は大事だが、その一つひとつをすべての人が理解して活用することを求めるのは酷なのではないだろうか。
先の漢字のたとえでいうならば、各漢字の意味を個別に覚えるというよりも「さんずいへんの漢字はだいたいこういうことに関係している」という認識を育てることに近い。そういった柔軟な認識は、予測不可能なことが起こる世の中でどう行動するか自分で判断し生きてゆくための強い武器になると私は考える。