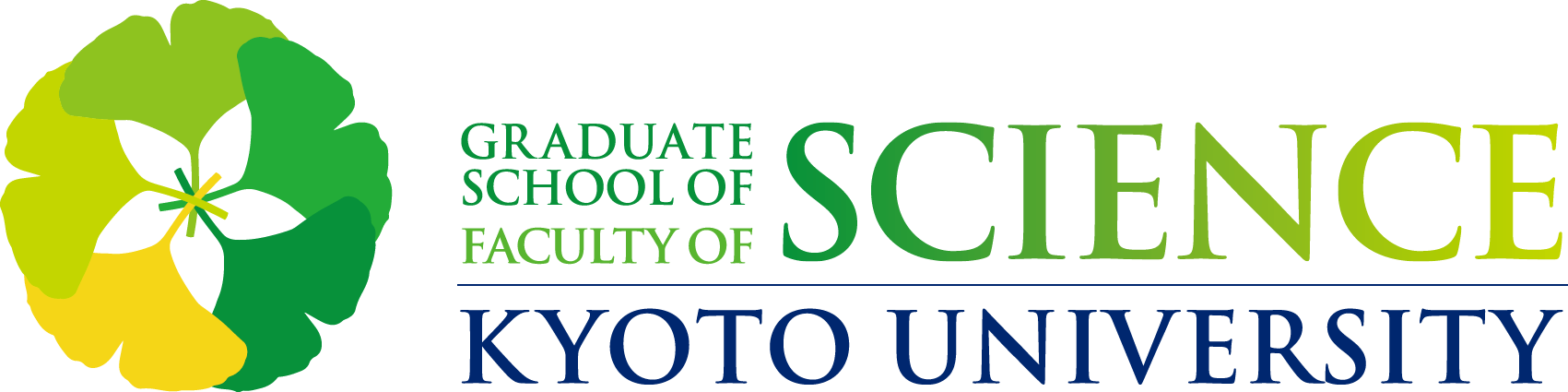愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター・教授 土屋 卓久

誕生から46億年が経過した現在でも地震や火山活動が続く地球は「生きている惑星」である。約100年前、ウェゲナーが大陸移動説を唱えた。1960年代になり海洋底拡大などプレートの水平移動の証拠が見つかり、「プレートテクトニクス」の概念が確立した。複数のプレートの境界に位置する日本は、世界の中でも特に地殻変動と密接に暮らしている国の一つだ。海洋のプレートと大陸のプレートが衝突すると、密度の大きい海洋プレートが大陸プレートの下部に沈み込む。日本周辺でいえば、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込んでいる。しかし沈み込んだプレートが地球内部をどこまでも深く沈むのか、途中で浮き上がり地表に戻るのか、ある深さで停滞するのか、地球深部は望遠鏡のように直接観測する手段がなく、いまだはっきりとは理解されていない。探査機が太陽系の外縁にまで到達する現在でも、地球深部はいまだ人類が未踏の領域「ラスト・フロンティア」なのである。
半径約6400 kmの地球内部は深くなるにつれ温度と圧力が増加し、地球中心では約364万気圧、約6000 Kに達する。非常に高い温度圧力のため、地球深部の直接掘削はほぼ不可能である。上部マントル物質は地表でも採取できる場合があるが、それより下にあるものは採取できない。直接見ることができない地球内部の研究は間接的な方法にたよらざるを得ない。地震波速度や密度などの観測データを岩石や鉱物の高温高圧物性に基づいて解釈することにより、地球深部の様子を推定する。高温高圧条件下の物性研究には二つの方法がある。一つは高温高圧実験と呼ばれる方法で、超硬合金やダイヤモンドを押しつけあったり火薬やレーザーを爆縮させたりして物質に高圧力を発生させる。特に超硬合金を用いる方法は1960年代に京大出身で阪大基礎工学部教授となった川井直人によって先駆的研究がなされ、その後も我が国が主導して技術開発が進展した。現在、川井型マルチアンビル装置と呼ばれる大型プレスの世界最大の装置が愛媛大学に設置されている。一方、実験的方法にも限界があるため、数値シミュレーションなどの理論的アプローチも重要である。特に量子論に基づく第一原理電子状態計算法の有用性が、計算機科学の発展に伴って広く認識されるようになっている。
地球深部科学における長年の謎の一つに、地球全体の体積の半分以上を占める下部マントルが上部マントルと独立して対流運動をしているのか、両者が一体となって全体で対流運動しているのかという問題がある。この謎を解くカギが下部マントルの平均化学組成である。我々の研究グループでは第一原理計算法を応用してマントル温度圧力条件においてモデル岩石の地震波速度(P波及びS波)及び密度を求め、観測値と比較することで下部マントル組成を推定した。その結果、上部マントルと同じ化学組成モデル(パイロライト)が下部マントルでも実際の地球の観測値と最もよく一致するという結果を得た。このことは、上下部マントルが一体となって運動しており、表層から沈み込んだ海洋のプレートはマントル全体の流れにのって、下部マントル深部へと沈み込んでいることを示唆している。
一方、深さ2900 kmの核とマントルの境界領域では、地震波速度が場所によって顕著に変化する不思議な性質が観測されている。特に環太平洋地域の下部ではS波速度が平均より1~2%程度速く、中央太平洋やアフリカの下部では逆に1~2%程度遅い。今世紀に入り超高圧実験や数値計算の進歩により、マントル最下部その場条件での物質の安定性や弾性特性の定量解析が可能となった。その結果、東工大グループの実験や我々のグループの計算から下部マントル物質の新たな相転移(ポスト・ペロブスカイト転移)がマントル最深部で生じること、この相転移が定圧力の下では相対的に低温の場合に生じやすいこと、そして相転移によりS波速度が2%程度上昇することなどが判明した。これらから、環太平洋地域のような沈み込み帯では冷たいプレートがマントル底部まで到達し周囲を冷やすことで相転移(高速度異常)が生じるのに対し、相対的に暖かい中央太平洋下部では相転移があまり生じていない(低速度異常)と考えられ、観測される地震波の不均質構造が解釈できる。冷たいプレートがマントル底部まで沈み込んでいるとするモデルはまた、マントルの化学組成から推察されるプレートの挙動とも調和的である。このように超高圧物性に基づく地球深部の定量研究が進んでおり、現在では同様のアプローチが鉄ニッケル合金からなる中心核にも応用されつつある。